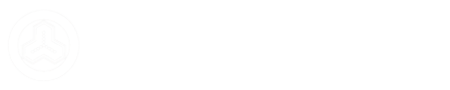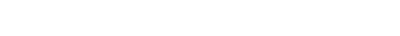毘沙門天とは

毘沙門天と多聞天の違い

日本では七福神や四天王として知られている毘沙門天ですが、その前身はインド神話に登場する「クベーラ」という財宝の神様です。
このインドの財宝神クベーラには、サンスクリット語で「ヴァイシュラヴァナ」という呼び名もあり、この「ヴァイシュラヴァナ」という音が中国語で訳されて「毘沙門」となりました。
毘沙門という表記は、ヴァイシュラヴァナを中国で音写したものですが「すべてのことをいっさい聞きもらさない知恵のある者」、「よく聞く所の者」という意味にも解釈できるため、多聞天(たもんてん)とも訳されました。
「毘沙門天」と「多聞天」は、同一神で日本では四天王の一尊として造像安置する場合は「多聞天」、独尊像として造像安置する場合は「毘沙門天」と呼ぶのが通例です。
毘沙門天の眷属と像の形
四天王と毘沙門天
四天王
十二天と毘沙門天
七福神と毘沙門天
七福神
七福神とは、日本で信仰されている七体の福の神を指します。これらの福の神の由来は様々で、ヒンドゥー教、仏教、道教、神道などが挙げられます。歴史的には七福神に属する神々は一定ではなく、様々な様式があったといわれています。現在は、毘沙門天、恵比寿、寿老人、大黒天、福禄寿、弁財天、布袋が七福神であるとされることが多いようです。
これら七福神は、インドの神様だったのが大黒天、毘沙門天、弁財天、中国の神様だったのが福禄寿尊、布袋尊、寿老人、そして唯一日本の神様が恵比寿となります。
なお、大岩山毘沙門天境内には本堂西側に山王権現と並び、大黒天が祀られております。